はじめまして、OSAKIです。私は司法試験に合格しています。受験資格は、ロースクールを卒業して得ました。ロースクールでの生活を踏まえた合格体験記を書いておこうと思います。
ロースクールでの生活
司法試験の受験資格は、予備試験に合格するか、ロースクールに進学して卒業することで得ることができます。私は、地方国立大学のロースクール(既修者コース)に入学しました。ロースクール入試は、学部3年生の頃から本格的に対策を始め、アガルートの重要問題習得講座やロースクール入試対策講座を使って学部4年のときになんとか合格することができました。
私のロースクールでは、既習1年目から基本7法を詰め込むようなカリキュラムが採られています。既習1年目では、授業の予習復習で手一杯でなかなか司法試験の勉強をすることができませんでした。しかし、授業は司法試験を意識してなされるものも多く、授業や期末試験を頑張ることが司法試験の対策に直結していたと思います。
授業がある期間は、授業が終わった後予習復習をこなし、夜22:00か23:00あたりに帰宅するという生活をしていました。土日も勉強に充てていましたが、テスト期間以外は友達と遊んだり飲みに行ったりしていました。勉強がつらいなと思った時期もありましたが、ロースクールでの生活は全体的に充実したものでした。ただ、とても体調を崩しやすくなっていたので、体調管理にはもっと気をつければよかったなと思います。
司法試験の勉強方法
司法試験には短答式試験と論文式試験があり、試験日4日間のうち3日間かけて論文式試験を行い、残りの1日で短答式試験を行います。短答式試験では憲法、民法、刑法の3科目が出題されます。論文式試験では、これに加えて、行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、選択科目の計8科目が出題されます。配点は、短答175点満点、論文800点満点で計算されます(総合点の計算では論文の点数に800分の1400をかけるため、総合点の合計は1575満点となります)。短答式、論文式のそれぞれについて私が行った勉強を紹介します。
〇短答式
短答対策を始めたのは、本番約半年前の12月頃からです。周りはもっと早くから短答の問題を解いていたので、開始時期としては少し遅いかなと思います。ただし、私は、予備試験の短答式試験を受験したことがあるので、本当にゼロから過去問を解き始めたわけではないです。
1日で民法10問、憲法刑法5問という風にノルマを決めて短答過去問パーフェクトを解いていきました。しかし、授業の予習復習や定期試験対策をしなければならない期間もあったため、全く計画通りにはいきませんでした。また、足切りされることはないだろうと短答式試験を甘く見ていました。その結果、3月に受けた模試で、予想足切りラインぎりぎりの得点(175点満点中81点)しか取れませんでした。
自己採点をして模試の結果が分かった次の日から、短答対策にかなり時間をかけるようになりました。勉強時間の半分かそれ以上を短答に充てていたと思います。やり方は、短答過去問パーフェクトを前から解いていって、間違えたところに印をつけ、間違えた問題を繰り返すという方法です。憲法は時間をかけてもコスパが悪いと思っていたので、そんなに時間をかけていません。人権分野は、判例百選を確認しながらやりました。総論統治は、得点源にできるよう合計4回ほどは解きなおしました。民法は、判例六法に間違えた部分をまとめ、隙間時間に条文の素読も行いました。量が多く1周するのにも時間がかかりますが、しっかりと時間をかければ点数も安定するので、時間をかけるべきだと思います。刑法は、他の科目に比べて本番も過去問とほぼ同じ問題がでる傾向にあると分析していたので、まとめノートなども作らず短答過去問パーフェクトを解いて解説を見ることを繰り返しました。結果として、刑法の得点はよかったので、やり方は間違っていなかったと思います。
これらの対策をして、短答式試験の前日に各科目間違えやすいところを一気に見返して本番に臨みました。本番の結果は合計138点でした。個人的にはかなり良い結果だったので、最後の追い込みが報われて嬉しかったです。
〇論文式
・過去問
司法試験は、論文式試験が山場です。過去問を解くことを対策の中心としました。ロースクール入試のときに重要問題習得講座をやった以外、問題集はほとんどやっていません。ただし、授業では問題集の問題を扱ったりしていたので、授業で扱った範囲で過去問以外の問題も結構解いています。司法試験の過去問に触れ始めたのは、ロースクールに入学して少ししてからです。自主ゼミを組んで週に1回過去問の検討をする形式でやり始めました。最初は全然書けませんでしたが、時間を測って何も見ずに書いてみて、出題趣旨や採点実感を見るようにしました。既習1年目の秋くらいまで、司法試験対策はこれくらいしかしていませんでした。秋になると、過去問を計画的に解いていこうと思い、エクセルで表を作りました。内容としては、行政法、刑訴法は全年度分、民法は5年分、選択科目の経済法はA,Bランクの問題、それ以外は直近10年分をやると決めました。在学中受験なので時間がなく、やるべき年度を絞ったのです。行政法と刑訴法をすべてやると決めた理由は、出題が過去問の焼き直しである傾向が強かったからです。民法は、範囲が広すぎて過去問をやりこむにはコスパが悪いと思ったので、授業の復習や論証の暗記を網羅的にやるにとどめることにしました。それ以外の科目は、本番までの時間との兼ね合いで、だいたい10年分くらいやれば大丈夫だろうと考えてこのような計画にしました。やり方としては、自主ゼミで起案するもの以外は、丁寧めの答案構成をしました。復習に1時間以上使っていたので、フルスケールで起案をしている時間がなかったからです。そして、本番までにだいたい計画通りやりきることができました。
過去問検討の際は、過去問をやる目的を意識していました。司法試験は、適用する条文がわかって、その要件効果のうち問題となる部分を把握し、適切な論証を張り付けることができれば合格すると考えていたので、その能力を得るためにはどのように過去問をすることが効率的かを考えてやっていました。科目によって細かい違いはありますが、どの科目も答案構成をした後、適用条文を含めた全体の流れや論証で参考となる部分を採点実感等から抽出して論証集に書き込んでいくという作業をしました。採点実感等は司法試験委員会が書いていることから、このように書けばとりあえず大丈夫だろうという安心感が得られ、論証を暗記する際にも不安なく覚えられるので良かったと思います。わからないところは基本書にあたることもありましたが、授業以外で基本書はほとんど使用していません。
・論証集
私は、司法試験対策に論証集を使っていました。公法系と経済法以外は、アガルートの市販の論証集を使用していました。憲法は、辰巳の合格思考憲法、行政法は基本行政法判例演習をまとめ教材として使用していました。経済法は、加藤ゼミナールの教材です。これらの教材に授業のメモ等を記載していました。私は、ロースクール入試や定期試験を受けた感覚で、論証を暗記してアウトプットすることができれば比較的上位に入ることができると思っていたので、毎日少しは暗記の時間を設けるようにしていました。
模試
模試は、3月に受けました。早めに受けておけば、模試で課題が見つかったとしてもそれを修正する時間が比較的残されていると考えたからです。模試の結果は短答やいくつかの科目がかなり悪かったですが、論文に関しては採点が本番とはかなり異なるものと予想されることから、模試では論証を覚えているかや時間配分などを確認することを目的としました。模試を受けてみて、司法試験の実際の日程で問題を解くことは初めてだったので、かなりしんどかった記憶があります。ただ、結局本番の方がしんどかったです。
本番
ホテルに持って行った教材は、六法と論証集と短答問題集のみです。間違いやすいところをだいたいチェックしていたので、試験前はそこを見返していました。1日目の公法系と選択科目の手ごたえが悪かった(結果もよくなかった)ですが、終わった科目のことは気にせず、前を向いて受けきることを心がけました。
まとめ
以上が、私の司法試験の合格体験記になります。何かの参考になれば幸いです。

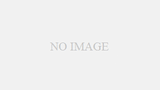
コメント